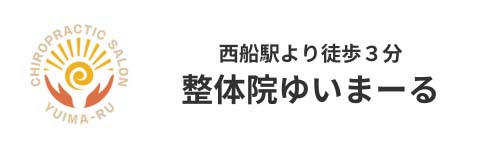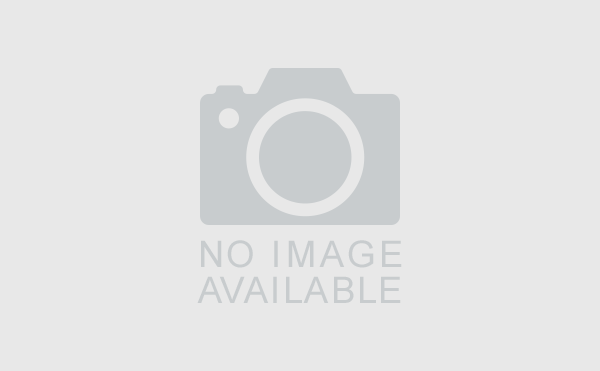【施術事例】逆流性食道炎・胸やけが改善!60代女性Hさん‐船橋市西船在住
はじめに:逆流性食道炎は「胃だけの問題」ではない
初めまして、整体院ゆいまーるの山城です^^
今回は逆流性食道炎と胸やけでお悩みのHさんについての記事を書いて行きます。

慢性的な胸焼け、喉の違和感、そして何とも言えない胃のムカムカ…。これらの症状に悩まされている方にとって、逆流性食道炎は日々の生活の質を著しく低下させる深刻な問題です。しかし、多くの人が「胃酸の出過ぎが原因」と考え、薬で症状を抑えるだけの対症療法に留まりがちです。
今回ご紹介するのは、船橋市西船在住の60代女性、Hさんの施術事例です。Hさんは、病院で逆流性食道炎と診断され、薬を飲んでも改善しない症状に苦しんでいました。
しかし、私たちは彼女の身体を「胃」だけでなく、全身の繋がりとして捉えることで、根本的な原因にアプローチ。最終的に、長年の悩みを解消へと導くことができました。
この記事では、逆流性食道炎という病気のメカニズムから、Hさんの身体が抱えていた真の問題、そして私たちが提供した施術とセルフケアの全容を詳細に解説していきます。
もしあなたが今、逆流性食道炎の症状に悩まされているなら、この記事が参考になれば幸いです。
第1章:逆流性食道炎とは何か?―なぜ胃酸は逆流するのか?
逆流性食道炎の基本知識
逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃酸、消化酵素など)が食道へ逆流することで、食道の粘膜に炎症が起こり、ただれたり傷ついたりする病気です。
本来、胃の粘膜は強力な胃酸に耐えられるようにできていますが、食道の粘膜は酸に弱いため、逆流が繰り返されると炎症を起こしてしまいます。これが、胸焼けや喉の違和感といった不快な症状の正体です。
逆流のメカニズム:下部食道括約筋と腹圧の関係
通常、食道と胃の境目には「下部食道括約筋」という、まるで胃のフタのような役割を果たす筋肉があります。食べ物が胃に入った後はこの筋肉がしっかりと締まり、胃の内容物が逆流しないように防いでいます。
しかし、この機能が低下すると、胃酸が逆流しやすくなります。機能が低下する主な原因は多岐にわたりますが、代表的なものを以下に挙げます。
- 下部食道括約筋の緩み:加齢とともに筋肉は緩みやすくなります。また、高脂肪食は消化に時間がかかり、胃酸の分泌を促進するため、括約筋に負担をかけることがあります。
さらに、肥満や妊娠、きついベルトなどによる腹圧の上昇も、括約筋を押し上げて緩ませる一因となります。 - 胃の内圧上昇:食事の量が多すぎる、食後すぐに横になる、前かがみの姿勢をとる、炭酸飲料を飲むといった行動は、胃の内圧を急激に高めます。これにより、括約筋が押し開けられ、胃酸が食道へと逆流しやすくなります。
逆流性食道炎の主な症状
船橋市西船在住Hさんがお悩みの逆流性食道炎の症状は非常に多岐にわたり、人によって現れ方が異なります。
- 胸やけ:みぞおちから胸、のどにかけて焼けるような、ヒリヒリする不快感。最も一般的な症状です。
- 呑酸(どんさん):胃酸が逆流し、口の中に酸っぱいものがこみ上げてくる感覚。
- 胸の痛み:心臓の病気と間違われることもあります。
- のどの違和感:のどに何かが詰まっているような感じや、イガイガする感じ。
- 咳やぜんそく:胃酸がのどや気管にまで達すると、慢性的な咳やぜんそくのような症状を引き起こすことがあります。
- 声がれ:声帯に炎症が起こることで声がかすれることもあります。
これらの症状は、食後や前かがみになったとき、就寝中などに起こりやすくなる傾向があります。
第2章:胸やけでお悩みHさんの来院経緯と問診

船橋市西船在住Hさんが来店された経緯
2025年1月15日、Hさんが当院にご来店されました。彼女は当院がオープンした2023年から、その存在は知っていたものの、なかなか一歩を踏み出せずにいたそうです。
しかし、最近になって「なんとなく胃のムカムカ」を感じ、病院で検査を受けたところ、逆流性食道炎と診断されました。
「どうにか改善できないか」とインターネットで情報を探していたところ、当院のウェブサイトにたどり着きました。そこで、逆流性食道炎にも対応していることを知り、「もしかしたら、ここなら何とかしてくれるかもしれない」と、今回の来院を決意されたそうです。
Hさんの問診:言葉にならない不調のサイン
問診を通じて、Hさんの身体が抱えるさまざまな問題が明らかになってきました。
- 主訴:逆流性食道炎。普段は気にならないが、忙しさや疲れが溜まると、胃がムカムカし、吐き気のような症状を感じるとのこと。
- 病院での診断:胃カメラ検査では、「胃の入り口付近が少し荒れている程度で、特に気になる異常は見当たらない」と診断されていました。
このことは、器質的な問題(物理的な病変)よりも、機能的な問題(身体の働きが悪くなっていること)が大きいことを示唆していました。 - 既往歴:4年前にバセドウ病と診断され投薬治療済み。3年前に交通事故で軽いむち打ちを経験。去年の11月には右足首を捻挫。
- 服用中の薬:骨粗しょう症とコレステロールの薬を服用中。
- 生活習慣:運動はしておらず、足の冷え性も自覚していました。
- 自律神経:ストレスレベルを5段階で評価してもらうと「4」と高め。便秘や下痢を繰り返すこともわかり、自律神経の乱れが強く疑われました。
これらの問診結果から、Hさんの逆流性食道炎は、単に胃酸が出過ぎているだけでなく、自律神経の乱れ、姿勢の悪さ、そして全身の筋肉の緊張が複雑に絡み合っている可能性が高いと判断しました。
第3章:身体の声を聞く検査:見えない原因を可視化する
問診で得た情報を裏付けるため、私たちは以下の検査を行いました。
- 脊柱の粘弾性(柔軟性):背骨一つひとつの動きの硬さや、周囲の筋肉の緊張を調べます。
- 骨盤のズレ:骨盤の傾きや歪みをチェックします。
- お腹の圧痛や張り感:お腹を優しく触診し、内臓の緊張や動きの悪さを探ります。
検査結果から読み解くHさんの身体
検査の結果は、私たちの仮説を裏付けるものでした。
- 脊柱の粘弾性:背中全体の強い緊張が認められました。特に、左の胸椎7番(T7)付近が硬くなっていることが判明しました。
- 考察:背中全体の緊張は、慢性的な肩こりや肋骨の柔軟性低下を表し、普段から呼吸が浅いことや、心臓や肺の動きが悪い可能性を示唆します。また、T7は胃の神経支配と関連が深く、左のT7の硬さは胃の機能障害があることを強く示しています。
- 骨盤のズレ:仙骨が後湾気味になっていました。
- 考察:仙骨が後湾すると、背骨全体のカーブが崩れ、猫背になりやすくなります。この姿勢は、胃や腸などの内臓を圧迫し、機能低下を引き起こしやすいと言われています。
- お腹の圧痛や張り感:みぞおち部に強い圧痛があり、左の下腹部にも圧痛が確認されました。また、お腹全体が張っていました。
- 考察:みぞおち部の圧痛は、胃や横隔膜の機能障害、そして交感神経が優位な状態(ストレス)を表します。左下腹部の圧痛は、場所的にS状結腸に当たり、便秘や結腸自体の機能障害を示唆します。お腹全体の張りは、内臓全体の動きの悪さや、自律神経の乱れによる腸の不調を表しています。
これらの検査結果と問診を合わせると、Hさんの逆流性食道炎は、単に胃の問題ではなく、自律神経の乱れ、姿勢の悪化、そしてそれに伴う内臓機能の低下が複合的に絡み合って引き起こされていることが明らかになりました。
第4章:施術と経過:根本から変えるアプローチ
船橋市西船在住Hさんの身体が抱える問題を一つひとつ解決するため、以下の施術を行いました。
施術①:背骨と肋骨の調整
まず、背中の胸椎周辺の筋肉を丁寧にほぐし、肋骨をねじるように関節に刺激を入れていきました。これにより、胃の神経支配と関連するT7付近にアプローチし、胃の働きをサポートします。同時に、胸椎付近にある交感神経管に刺激を入れ、リラックスを促し、自律神経のバランスを整えることを目指しました。時間にして約10分程度。
施術②:内臓マニピュレーション
次に、直接胃にアプローチする内臓マニピュレーションという手技を行いました。これは、お腹の上から優しく手を当て、胃のぜん動運動を手でサポートし、胃の動きを正常に戻していく施術です。ソフトな刺激ですが、Hさんの身体はすぐに反応し始めました。約5分程度の施術でした。
施術③:仙骨の調整と全身のバランス調整
仙骨の後湾を矯正し、姿勢の土台を整えました。この時点で、Hさんから「なんか背中とお腹がすごいスッキリしてます!」という驚きの声が聞かれました。再度検査を行うと、背中の凝り感はまだ残っていたものの、先ほどまでの強い緊張は無くなり、みぞおち部の圧痛や張り感も半分以下に軽減していました。
この時点で約35分が経過し、残りの時間で腕やふくらはぎなど、他の凝っている箇所をほぐし、全身の血行を促しました。施術終了後、Hさんは「すごくスッキリした」と笑顔を見せてくれました。
1週間後の変化と、継続的なメンテナンス
Hさんには、身体の変化を観察するため、1週間後に再度ご来院いただくようお伝えしました。1週間後、Hさんは「胃のムカムカはほとんど感じなくなった」と嬉しい報告をしてくれました。肩の凝り感はまだ残っているものの、身体全体が軽く、気分も良いとのことでした。
この日も前回同様の施術に加え、腸の動きの悪さにも着目し、腸への刺激も加えました。私たちはHさんに、「症状が出なくなっても、ストレスや疲れが溜まると再び症状が出る可能性があります。定期的なメンテナンスとして、1~2ヶ月に1回のペースで通えると良いでしょう」と伝えました。
Hさんはそれ以来、最初の1ヶ月で5回ほど集中的にご来院いただいた後、現在は1〜2ヶ月に1回のペースでメンテナンスに通われています。そして、胃の調子はすこぶる良いとのことです。
まとめ:逆流性食道炎でお悩みの60代女性Hさん
Hさんの事例は、逆流性食道炎が単に胃の問題ではなく、自律神経、姿勢、内臓機能といった全身のバランスの崩れが引き起こす症状であることを改めて示してくれました。病院で「異常なし」と診断されても、それはあくまで器質的な問題がないというだけであり、身体の機能が低下している可能性は十分にあります。
Hさんのケースでは、
- 背骨と肋骨の調整で自律神経を整え、
- 内臓マニピュレーションで胃の機能自体を改善し、
- 骨盤の調整で姿勢の土台を築く
という多角的なアプローチが、長年の悩みを解決する鍵となりました。
船橋市・西船橋エリアで逆流性食道炎・胸やけならゆいまーるへ!

もし、あなたが今、薬を飲んでも治らない逆流性食道炎の症状に悩まされているなら、それは身体が「根本的な改善」を求めているサインかもしれません。船橋市西船にある当院では、あなたの身体と真摯に向き合い、根本からの改善を目指すお手伝いをいたします。一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。