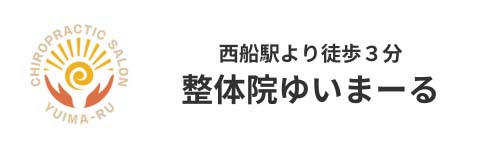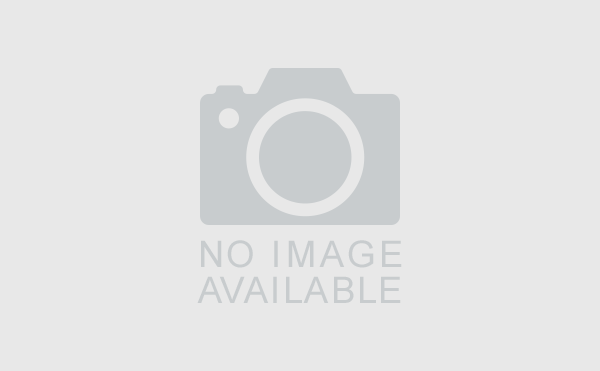【施術事例】疲れによる頭痛・倦怠感が改善!船橋市印内在住・40代男性Kさん
はじめに

こんにちは。船橋市西船にある整体院ゆいまーるの山城です^^
この度、皆様にご紹介するのは、長年にわたり慢性的な頭痛と倦怠感に苦しんでいらっしゃった40代男性のKさん(船橋市印内在住)の施術事例です。
Kさんの事例は、多くのビジネスパーソンが抱える「原因不明の不調」に対する、根本的な解決の糸口を示すものとなるでしょう。
Kさんは、お仕事の都合上、月に2〜4回という頻度で全国各地へ出張される多忙な日々を送っていらっしゃいました。
しかし、その出張がKさんにとって大きな負担となり、「ホテルで熟睡できない」「翌朝は頭がズキズキと激しく痛む」「日中の集中力が持続しない」といった深刻な症状に悩まされ続けていたのです。
これらの症状は、日常生活にじわじわと、しかし確実に支障をきたし、Kさんの生活の質を低下させていました。
「整形外科に行くほどではないけれど、明らかに体調が悪い」。
このような「原因不明の頭痛と倦怠感」は、特にKさんのように出張が多いビジネスパーソンに非常によく見られる傾向があります。
多忙な現代社会において、知らず知らずのうちに蓄積される身体的・精神的ストレスが、様々な不調として表面化することは珍しくありません。
しかし、その根本原因に気づき、適切なアプローチを行うことで、これらの不調から解放される道があることを、Kさんの事例は雄弁に物語っています。
この記事では、船橋市印内在住Kさんが当院にご来院されてから、症状が着実に改善していくまでの詳細なプロセスを、具体的な検査内容や施術内容とともに、深掘りして解説していきます。
船橋市印内周辺にお住まいで、Kさんと同様の「原因不明の頭痛と倦怠感」といったお悩みを抱えていらっしゃる方々にとって、この情報が自身の症状を理解し、改善に向けた一歩を踏み出すための貴重な参考となれば幸いです。
Kさんの体験を通して、皆様自身の「治らない」と諦めていた不調にも、まだ見ぬ根本原因と、それを解決する可能性が秘められていることに気づいていただけることを願っています。
頭痛・倦怠感でお悩みのKさんについて
来院された経緯|「出張後に必ず頭痛が出る」その理由とは?

Kさんの不調は、単なる疲れやストレスでは片付けられない、明確なパターンを持っていました。
それは、「出張後に必ず頭痛が起きる」というものでした。
この一貫した症状は、Kさんの身体のどこかに、出張という環境変化に反応して不調を引き起こす根本的な要因が潜んでいることを示唆していました。
2025年5月中旬、当院に船橋市印内在住のKさん(40代・デスクワーク)がご来院されました。
Kさんは、仕事の性質上、月に平均2〜4回、1泊~2泊程度の出張が日本全国各地であるとのことでした。
新幹線や飛行機での長時間の移動、慣れない環境でのホテル泊、自宅とは異なる硬さや高さのベッド、そして長時間の会議や商談といった、身体的にも精神的にも大きな負担がかかる生活スタイルを日々送っていらっしゃいました。
ご本人が来院時に訴えられた主な症状は以下の通りです。
- 出張翌朝には必ず頭痛が起きる。特に右側がズキズキと激しく痛むのが特徴。
- 頭痛の強さは、Kさんの主観では10段階中「10レベル」と表現されるほど、最も強い痛みを感じていた。
- 朝から体がだるく、「鉛のように重い」と感じ、布団から起き上がることすら億劫になる日もあった。
- 視界がかすむことがあり、仕事中も集中力が続かず、業務効率が著しく低下していた。
- 呼吸が浅くなり、「ため息が増えた」とご自身でも自覚されていた。
- 以前、複数の医療機関を受診したものの、「ストレス性」と診断されるだけで、具体的な治療法や根本的な解決策は提示されなかった。
Kさんはもともと健康意識が非常に高く、日頃から食事の栄養バランスや睡眠の質にも細心の注意を払っていらっしゃいました。
健康的な生活を送ることで、不調を未然に防ぎたいという意識が強かったにもかかわらず、それでもなお症状が改善せず、むしろ悪化していくことに深い悩みと不安を抱えていらっしゃいました。
そんな折、船橋市印内在住Kさんは 当院の前を通りかかった際に、「整体で自律神経も整えられるかもしれない」という考えが脳裏をよぎり、その場でスマートフォンから当院のウェブサイトを検索し、ネット予約をされたとのことでした。
Kさんの事例は、「治らない」と諦めていた症状にも、まだ見ぬ根本原因が存在し、それを解明しアプローチすることで改善の道が開かれる可能性を示唆しています。
初回検査の結果|身体のあちこちに“見えない負担”が
船橋市印内在住Kさんの長引く不調の根本原因を特定するため、当院では、姿勢、関節、内臓、呼吸、そして頭蓋という5つの異なる視点から、極めて詳細な検査を実施しました。
この多角的なアプローチにより、Kさんの身体のあちこちに潜在していた「見えない負担」が明らかになったのです。
検査結果は、Kさんが訴える症状と密接に関連していることが判明しました。
◆ 頸椎(首の骨)の可動制限:
Kさんの首の骨(頸椎)には顕著な可動制限が見られました。
- 後屈(上を向く動作):動きが非常に硬く、首の付け根、特に首の根本に強い痛みを訴えられました。
これは、デスクワークやスマートフォンの使用など、前傾姿勢が続くことで首に負担がかかっている典型的な兆候です。 - 前屈(下を向く動作):強い張り感はあったものの、痛みは伴いませんでした。
- 左右回旋(左右を向く動作):左への回旋時には明確な可動域制限が認められ、右への回旋時には鋭い痛みが生じました。
これは、首の筋肉だけでなく、頸椎の椎間関節にも問題が生じている可能性を示唆しています。 - 側屈(横に倒す動作):左側へ倒した際に、右側の首に痛みが生じました。
これは、首の左右のバランスが崩れていることを示しています。
◆ 胸郭(肋骨と背骨)の硬さと呼吸の浅さ:Kさんの胸郭、つまり肋骨と背骨で構成される胸の部分は、非常に硬く、動きが悪くなっていました。
- 胸郭の動きが制限されているため、深呼吸が十分にできない状態でした。
呼吸が浅いことは、自律神経の乱れや全身の酸素供給不足に直結します。 - 特に、呼吸において重要な役割を果たす横隔膜の可動性が著しく乏しいことが判明しました。
これは、呼吸の「ポンプ」としての機能が十分に働いていない状態であり、Kさんが訴えていた「呼吸が浅い」「ため息が増える」という症状の根本原因の一つと考えられました。
◆ 頭蓋骨(蝶形骨・側頭骨)の硬直:
Kさんの頭蓋骨、特に蝶形骨と側頭骨に強い緊張と硬直が見られました。
- 頭部の筋肉である側頭筋も強くこわばっており、触診でもその硬さが明確に確認できました。
- Kさんが訴える頭痛の部位(特に右側)と、この頭蓋骨の硬直部位が一致していることから、Kさんの頭痛が頭蓋骨の歪みや緊張に由来する症状である可能性が非常に高いと判断されました。
◆ 肝臓の緊張(内臓疲労):
身体の外側だけでなく、内臓の状態も詳しく検査しました。
その結果、Kさんの肝臓に強い緊張が見られました。
- 右側の肋骨下あたりに強い圧痛と硬さが確認されました。
これは肝臓が疲労している兆候であり、出張による不規則な生活や食生活の乱れが影響している可能性が考えられました。 - さらに、右肩と右腰の可動性が著しく低下していることが判明しました。
これは、医学的にもよく知られている肝臓と関連する反射反応であり、肝臓の疲労が身体の他の部位にも影響を及ぼしていることを示唆していました。
これらの詳細な検査結果は、Kさんの「原因不明の頭痛と倦怠感」が、単一の原因ではなく、頸椎の歪み、呼吸機能の低下、頭蓋骨の緊張、そして内臓疲労(特に肝臓)といった複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされていることを明確に示していました。
これらの“見えない負担”を取り除くことが、Kさんの症状改善への鍵となることが明確になったのです。
施術内容|神経・内臓・頭蓋・呼吸を整える多面的アプローチ
初回検査で判明した船橋市印内在住Kさんの身体の複数の問題を解決するため、当院では神経、内臓、頭蓋、そして呼吸という4つの側面からアプローチする多面的な施術計画を立てました。
Kさんには、まず週1回ペースで合計3回の施術をご提案し、根本的な改善を目指すこととしました。
初回は、特にKさんが最も苦しんでいた「頭痛と倦怠感」に直結する呼吸と頭蓋、そして内臓に焦点を当てた調整を実施しました。
【1】胸郭と横隔膜の調整|「呼吸がラクになると頭痛が軽くなる」
施術の最初のステップは、船橋市印内在住Kさんの呼吸機能を正常化することでした。
Kさんが「呼吸が浅い」「ため息が増える」とご自身でも自覚されていたように、検査では胸郭(肋骨と背骨)の動きが悪く、深呼吸ができない状態が確認されていました。
特に、深呼吸時の胸の動きが左右で非対称であり、呼吸の要である横隔膜の可動性が著しく低下していたため、まずはこれらの部位の可動性を高める施術を行いました。
具体的には、胸郭の関節一つ一つを丁寧に調整し、硬くなっていた肋骨の動きを改善しました。
また、横隔膜に直接アプローチし、その動きをスムーズにすることで、より深い呼吸ができるように促しました。
この施術は、Kさんの自律神経のバランスを整え、全身への酸素供給を促進することを目的としています。
施術後、Kさんからは驚くべき変化が報告されました。
- 「息がスッと吸えるようになった」
- 「頭のモヤモヤがスーッと抜けた感じがする」と、具体的な感覚として、その変化を明確に感じていただけました。
実際、施術前に10段階中「10」という最悪のレベルだった頭痛の強さが、この胸郭と横隔膜の調整後には、なんと「5」にまで半減したのです。
Kさんはこの変化に非常に驚かれ、呼吸と頭痛の間には密接な関係があることをご自身で実感されていました。
この段階で、Kさんの表情には明らかに安堵の色が浮かんでいました。
【2】頭蓋骨と肝臓の調整|自律神経と右側症状の関連を探る
次に実施したのは、Kさんの症状と密接に関連していた頭蓋骨(特に蝶形骨と側頭骨)と肝臓の調整です。
Kさんの場合、初回検査で判明したように、身体の右側にのみ強い緊張や可動制限が集中していました。
このような左右差のある症状は、しばしば「肝臓由来の身体反応」として整体の現場でよく見られるパターンです。
肝臓は、体内で解毒や代謝といった重要な役割を担うだけでなく、自律神経、特に交感神経との関わりが非常に深い臓器です。
出張による寝不足、精神的ストレス、食生活の乱れといった要因は、肝臓に過度な負担をかけ、その機能低下を引き起こしやすいことが知られています。
肝臓の機能が低下すると、自律神経のバランスが崩れやすくなり、これがKさんの頭痛や倦怠感といった症状を悪化させている一因と考えられました。
この施術では、まず、硬くこわばっていた右側の蝶形骨と側頭骨に微細な圧を加え、頭蓋骨の歪みを調整しました。
これにより、頭蓋骨内の脳脊髄液の流れを促進し、脳の機能改善を促します。
同時に、右側の肋骨下にあった肝臓の緊張に対して、優しく、しかし確実にアプローチすることで、肝臓の機能回復を促しました。
頭蓋骨と肝臓を同時に整えるというこのアプローチは、神経と内臓のつながりをリセットし、自律神経のバランスをより効果的に調整することを目的としています。
施術直後、Kさんからはさらに大きな驚きの声が上がりました。
- 「首が急に柔らかくなった」
- 「さっきまでの頭痛が全然ない」
- 「こんなに体が軽くなるのは初めてだ」
- 印内在住Kさんは、これまでの自身の身体の重さや痛みが嘘のように消え去ったことに、心底驚かれている様子でした。この瞬間のKさんの笑顔は、私にとって大きな喜びとなりました。
その後の経過と現在の様子
初回施術での劇的な変化を経験された船橋市印内在住のKさんは、その後も当院が提案した週1回ペースでの施術を継続され、合計3回の施術を受けていただきました。施術を重ねるごとに、Kさんの身体は着実に回復し、症状は顕著に改善していきました。
2回目の施術後には、Kさんから喜びの声が聞かれました。
- 「出張明けでも頭痛がひどくならなかった」これまでのKさんにとって、出張明けの頭痛は避けられないものと認識されていましたが、2回目の施術後にはそのサイクルが断ち切られたのです。
これは、施術によってKさんの身体がストレスや環境の変化に耐えうる状態へと変化したことを明確に示していました。
そして、3回目の施術後には、Kさんの心理面にも大きな変化が現れました。
- 「出張が前より憂うつじゃなくなった」これまでは、出張が近づくたびに頭痛や倦怠感を予期して憂鬱な気持ちになっていたKさんですが、身体の不調が改善されたことで、出張に対するネガティブな感情が薄れ、むしろ前向きな気持ちで仕事に取り組めるようになったのです。
これは、単なる身体症状の改善にとどまらず、Kさんの生活の質そのものが向上したことを意味します。
現在、Kさんは以前のようなひどい頭痛や倦怠感に悩まされることはほぼなくなりました。月に2回のペースで当院にメンテナンス通院を継続されており、良好な身体の状態を維持していらっしゃいます。
メンテナンスを続けることで、日常生活の中で蓄積される小さな負担を早期に取り除き、症状の再発を予防することができています。Kさんの表情は以前よりも明るく、仕事にもプライベートにも精力的に取り組んでいらっしゃるご様子です。
日常へのアドバイスとセルフケア
Kさんの症状が劇的に改善した背景には、当院での施術効果だけでなく、船橋市印内在住Kさんご自身の高い健康意識と、私が提案したセルフケアを日々実践してくださった努力も大きく貢献しています。
施術と並行して、Kさんには以下のような具体的なセルフケアをご提案し、その実践を促しました。
- 1時間ごとに立ち上がり、背中・肩のストレッチを行う:デスクワークのKさんにとって、長時間同じ姿勢でいることは、首や肩、背中の筋肉に大きな負担をかけます。
1時間に1回という短い休憩でも立ち上がり、簡単なストレッチを行うことで、血流を促進し、筋肉の硬直を防ぐことができます。これにより、頸椎や胸郭の可動性を維持し、頭痛や倦怠感の予防につながります。 - 水分を1日1.5〜2リットル摂取し、血流促進:体内の水分が不足すると、血液がドロドロになり、血流が悪化します。これは、疲労物質の蓄積や自律神経の乱れに繋がる可能性があります。
1日あたり1.5リットルから2リットルを目安に水分をこまめに摂取することで、血流を良好に保ち、体内の代謝を促進し、肝臓への負担を軽減します。 - ホテルでは自分のタオルを使い、枕の高さを調整:出張時のホテルでの睡眠環境は、Kさんの頭痛のトリガーとなっていました。特に、枕の高さや硬さは首への負担に直結します。
ご自身の使い慣れたタオルを持参し、それを丸めるなどして枕の高さや硬さを調整することで、首への負担を最小限に抑え、質の良い睡眠を確保するようにアドバイスしました。これにより、出張中の身体へのストレスを軽減し、頭痛の発生を予防します。 - 寝る前はスマホやPCを避け、光刺激を減らす:スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、質の高い睡眠を妨げます。Kさんには、就寝前の最低1時間は、スマートフォンやパソコンの使用を避けるよう徹底していただきました。
これにより、脳への光刺激を減らし、スムーズな入眠と深い睡眠を促すことで、自律神経の安定化と身体の回復をサポートします。
こうした日々のセルフケアの積み重ねが、当院での施術効果を最大限に引き出し、自律神経の安定化と呼吸の正常化に大きく貢献しました。Kさんはこれらのアドバイスを忠実に実践してくださり、それが施術効果の持続と、以前のような不調からの解放に繋がったのです。セルフケアは、治療効果を補完し、患者さん自身が自分の身体と向き合い、健康を維持していくための強力なツールとなります。
まとめ|“あきらめていた不調”にこそ根本改善のヒントがある
船橋市印内在住Kさんの事例は、「病院に行くほどではないけれど、日常生活に明らかな支障がある不調」に悩まされている方がいかに多いかを浮き彫りにしています。
Kさんのように、長期間にわたり原因不明の頭痛や倦怠感に苦しみ、それが仕事やプライベートに深刻な影響を及ぼしているケースは決して珍しくありません。
もしあなたが以下のようなお悩みを抱えているのであれば、Kさんの事例は、あなたの身体にもまだ見ぬ「根本原因」が潜んでいる可能性を示唆しています。
- 頭痛薬が効かなくなってきた、あるいは服用頻度が増えてきた
- 出張や旅行のたびに体調が悪くなる、特に頭痛や倦怠感がひどくなる
- 日中に集中力が続かない、常に身体がだるいと感じる
- 病院では「ストレス性」と言われたが、根本的な解決に至っていない
このような方にこそ、当院がKさんに行ったような、構造(骨格、筋肉)、神経(自律神経)、内臓を統合的に整える整体アプローチが必要です。身体は一つであり、それぞれの部位は密接に連携しています。どこか一か所に問題がある場合でも、それが全身に波及し、複雑な症状を引き起こすことがあります。
当院の施術は、表面的な症状だけでなく、その奥に隠された根本原因を見つけ出し、身体本来の回復力を引き出すことを目指します。
「もう治らないのではないか」と諦めていた症状でも、私たちの身体には、自ら変化し、回復する力が備わっています。船橋市印内在住Kさんのように、長年の不調に苦しんでいた方でも、適切なアプローチとセルフケアによって、その身体は劇的に変化し、健康的で快適な日常を取り戻すことができるのです。
船橋市・印内エリアで頭痛・倦怠感にお困りなら!

当店は船橋市西船にあり印内在住のKさんのご自宅とは近い距離にありました。
Kさん以外にも印内エリアからは多数のご相談をいただいています。
あなたの体にも、まだ知られていない“根本原因”が潜んでいるかもしれません。もし、Kさんのように原因不明の不調でお悩みであれば、ぜひ一度当院にご相談ください。私たちは、あなたの身体に潜む「見えない負担」を明らかにし、根本的な改善へと導くお手伝いをさせていただきます。
※本記事の内容はご本人の同意を得て掲載しています。施術効果には個人差があります。